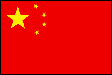 |
中国旅行をする時に役立つ情報 |
| メニュー TOPページ 中国 中国体験記 中国の地理 中国の地名 中国料理 中国関連news 台湾 韓国 インド シンガポール タイ リンク 更新日: 2008年10月26日 |
国名:中華人民共和国 People's Republic of China 首都:北京(BEIJING) 北京市の常住人口は1,633万人(2007年末)(2008年1月22日、人民網日本語版) 面積:959万6960km2(台湾を含む、日本の約25倍、米国とほぼ同じ、地球の陸地面積の6.4%) 人口:12億8,430万3,705人(世界の5人に1人は中国人)(2002年7月推計) 人口密度:134人/km2(2002年推計) 都市人口率: 43.1%(2008) 100万都市の数: 117都市(2006) 北京:1,581万 天津:1,075万 上海:1,815万 重慶:2,808万 出生率:1.32%(2006年)(2007年6月6日、人民網日本語版) 粗死亡率:6.4/1,000人/年(データブック・オブ・ザ・ワールド 2007、二宮書店) 乳児死亡率:26.0/1,000人(データブック・オブ・ザ・ワールド 2007、二宮書店) 平均寿命(男):70.0歳(データブック・オブ・ザ・ワールド 2007、二宮書店) 平均寿命(女):73.0歳(データブック・オブ・ザ・ワールド 2007、二宮書店) 一人あたりGNP:US$ 1500(データブック・オブ・ザ・ワールド 2007、二宮書店) 言語:漢語(中国語:北京語を中心とする普通話(標準語))。各地方言と少数民族語。 識字率(15歳以上):90.9%(2000年、中国教育報) 93.3%(男:96.5%、女:90.0%)(2007) 労働力人口:8億9,000万人(2005年) 宗教:憲法で信教の自由を保障。ラマ教、道教、仏教、イスラム教2~3%、キリスト教1%、無宗教。 独立:1912年2月12日、中華民国成立 :1949年10月1日、中華人民共和国成立 国連加盟:1945年10月24日 現憲法:1982年公布(93年3月 一部改正) 民族:漢民族93%、他にモンゴル族、回族、ウイグル族、チベット族等、56の少数民族 地形 ロシア、カナダについで世界で3番目に大きな国。東部沿岸の平原地帯から西へ進むにつれてしだいに標高が高くなる。東部は揚子江や黄河流域に広大な沖積平野が広がり、西部はパミール高原、崑崙山脈、天山山脈、チベット高原などの山岳と高原が連なり、その間にタリム、四川などの広大な盆地が展開している。 気候 全体的には温帯に属し、西乾東湿、北冷南暖の気候である。西部は大陸性気候で、モンゴルからタリム盆地にかけてステップと砂漠が広がり、チベット高原などの山岳地帯は高山気候である。東北地方は冬に寒冷な大陸性冷帯湿潤気候で、黄河、揚子江流域の華中は温帯モンスーン気候、華南は亜熱帯モンスーン気候である。 産業(2002年4月) 農業では、革命の象徴であった人民公社は、生産性が向上しないことから85年までに解体され、市場原理を重視した生産請負制を取り入れ増産に成功、万元戸とよばれる富農が出現している。 工業でも経営自主権を保障し、郷鎮企業とよばれる農民による小規模農村工業を認めるなどにより、生産性を向上させている。輸出品では繊維、衣類、日用雑貨が多い。さらに外貨と技術を獲得するため、「経済特区」「経済開発区」が誕生し市場経済化を進めている。特に香港周辺の開発は目ざましく「華南経済圏」を形成しつつある。90年には証券取引所もオープンした。沿岸部から始まった工業の近代化は内陸部に向かって広がりはじめている。 ◎国旗 中国の国旗は「五星紅旗(ごせいこうき)」ともいわれ、赤は共産主義のシンボルの色。大きな星は中国共産党を、小さな4つの星は労働者、農民、知識階級、愛国的資本家を表している。 ◎行政(2002年4月) 行政区画:22省、5自治区、4直轄市、1特別行政区 ・自治区:内蒙古、寧夏回族、新疆ウイグル、広西チワン族、チベット ・直轄市:北京市、天津市、上海市、重慶市 ・特別行政区:香港 ◎政治体制(2010年4月) 政体 :人民民主共和制。人民民主独裁の社会主義国家。 議会 :一院制(全国人民代表大会) 委員長:呉邦国 代表者数:2,979名(97年2月6日現在) 主要政党:共産党(党員 約5,800万人) 総書記:胡錦濤 国家主席:胡錦濤 政府要人:共産党:胡錦濤(総書記) 首相(国務院総理):温家宝(Wen Jiabao) 外相 :楊潔篪(外交部長) ◎内政(2002年4月) 江沢民総書記を中心とする集団指導体制の下、改革・開放政策による経済成長を最重要課題として近代化建設が推進されている。 江沢民政権は、各種問題(幹部の汚職・腐敗問題、国有企業や行政機構の改革、失業者の増大、少数民族問題、「法輪功」問題等)を抱えつつも、経済が順調に成長していることもあり、内政はこれまで比較的安定。 2002年秋には第16回党大会、2003年春には第10期全人代第1回全体会議を控えていることもあり、引き続き政治的・社会的安定を最優先する慎重な舵取りがなされている。 ◎外交基本方針(2002年4月) (1)平和共存五原則に基づく各国との関係発展 (2)覇権主義反対、世界平和の擁護 (3)第3世界との団結・協力の強化を標榜し「独立自主の平和外交」を展開 ◎軍事力(ミリタリーバランス98/99) 中国人民解放軍 総兵力282万人(陸軍209万人、海軍26万人、空軍47万人) 現在人員削減中 (1)予算:1,684億元(2002年度予算:約203億ドル、約2.7兆円) GDP比1.76%(対2001年度) (日本の国防予算は4兆9,395億円、約380億ドル、GDP比0.995%:2002年) 約4,099億元(2008年公表予算) (約5兆9,605億円:1元=14.54円換算) (約561.5億ドル:1ドル=7.3元換算) (2)兵役:徴兵(満18歳?22歳の男女)と志願兵の併用(陸・海・空軍一律2年) (3)兵力:総兵力約231万人(第2砲兵10万人含む):(陸軍160万人、海軍25万人、空軍42万人、作戦機約2,900機) 総兵力約210.5万人(陸軍約160万人、海軍約21.5万人、空軍約25万人)(ミリバラ2008より) ◎経済(2002年4月) 主要産業:農業、エネルギー産業、鉄鋼、繊維、食品 GDP:約9,600億ドル(1998年:7兆9,553億元) GDP:約1兆ドル(2001年:約9兆5,933億元、日本は4.14兆ドル(2001年)) 一人当たりGDP:850ドル(2001年。日本は32,605ドル(2001年)) 経済成長率:7.8%(98年) 経済成長率:7.3%(2001年。GDP対前年比) 物価上昇率:0.7%(2001年、消費者物価) 失業率:3.6%(2001年、都市部登録失業率) 国民総所得(GNI):1兆1309億8400万米ドル(2001年) 1人当たり所得(GNI/人):890米ドル(2001年) ◎総貿易額 (1)輸出:2,662億ドル(2001年) 7兆7,595億元(2006年) 1兆2,180億1,500万ドル(2007年)(数値は中国税関総署) 対日輸出額:1,020億7,129万ドル(2007年) (2)輸入:2,436億ドル(2001年) 6兆3,377億元(2006年) 9,558億1,800万ドル(2007年)(数値は中国税関総署) 対日輸入額:1,339億5,064万ドル(2007年) ◎主要貿易品目 (1)輸出:繊維・同製品、機械電気製品、石油・同製品、繊維原料(2001年) 機械電気製品、ハイテク製品、繊維・同製品(2007年、中国税関総署) (2)輸入:工業用機械、自動車、通信機器(2001年) 機械電気製品、ハイテク製品、集積回路・マイクロ組立部品(2007年、中国税関総署) ◎主要貿易相手国 (1)輸出:米国、香港、日本、EU(2001年) EU、米国、香港、日本(2007年、中国税関総署) (2)輸入:日本、EU、米国、韓国(2001年) 日本、EU、ASEAN、韓国(2007年、中国税関総署) ◎日系企業進出状況 企業数:22,650社(2006年末現在)(2007中国貿易外経統計年鑑) ◎在留邦人 人数:127,905人(香港、マカオ含む)(2007年10月、外務省ホームページ) ◎在日中国人数(在日華僑を含む) 560,741名(2006年、法務省統計) |
| ☆中国生活情報 ◎通貨(2002年4月) 中国の法定通貨は人民幣(レンミンピー:人民元:RMB)。であり、中国人民銀行が発行する。単位は「元」です。発音は“ユアン”です。紙幣には圓と印刷されています。補助単位は、角(ジャオ)と分(フェン)です。 紙幣は100元、50元、10元、5元、2元、1元、2000年10月からは20元の人民元紙幣が発行された。20元紙幣は赤茶色で、表に毛沢東の顔像、裏に桂林の景色が描かれている。 元の10分の1に当たる角、角の10分の1に当たる分の紙幣もそれぞれ3種類ある。また、1999年の建国50周年以降、毛沢東が印刷された新札が登場し、100元札は現在、2種類流通している。 硬貨は1元、5角、1角、5分、2分、1分の6種類だが、最近では、分は大型スーパーなどを除けばほとんど流通していない。 ◎紙幣(2002年4月) 1分、2分、5分、1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元、20元、50元、100元 1999年の建国50周年以降、毛沢東が印刷された新札が登場し、100元札は現在、2種類流通している。 2000年10月からは20元の人民元紙幣が発行された。20元紙幣は赤茶色で、表に毛沢東の顔像、裏に桂林の景色が描かれている。 ◎硬貨:6種類(2002年4月) 1分、2分、5分、1角、5角、1元 最近では、分は大型スーパーなどを除けばほとんど流通していない。 1元(ユアン(Yuan)/通称:クアイ)=10角(ジヤオ/通称:マオ)=100分(フェン) 1角(ジヤオ/通称:マオ)=10分(フェン) ・レート 1人民元=14.9円(2001年12月) 1人民元=16.24円(2002年3月1日) 1ドル=約7.3046元(2007年末)(数値は中国国家外国為替管理局) ・両替(2002年4月) 両替は外国人観光客が宿泊する3つ星以上のホテル、空港内の両替所、友誼商店、銀行でできる。銀行の営業時間は、各銀行ごと、また規模によっても異なる。 両替が可能な主な銀行は中国銀行と交通銀行。中国銀行の場合は通常、月~金曜日の9時~16時30分、土曜日は午前中の営業になる(場所によって日曜の営業もある)。空港内の銀行は年中無休、深夜でも営業しているため、日本での両替は不要だ。トラベラーズチェックの両替は市中銀行で可能だが、ホテルでは宿泊客に限られる場合もある。 他の国とは異なり、レートはどこでも同じ。100元札がいちばん大きい通貨単位なので、高額の日本円を両替するとたちまち財布が膨れ上がることになる。 友誼商店や大型ショッピングセンター、高級ホテルなど外国人が多く集まる場所の周辺には、決まって闇の両替屋がたむろしている。レートはかなりよく、市民の間でも闇両替が一般化しつつあるようだ。ただし、公安による摘発も少なくなく、外国人旅行者にはおススメできない。 北京市海淀区にあるデパート・当代商城に100元札、50元札を10元札に両替する「自動換零機」(自動両替機)が登場した。 タクシーに乗るときや小さな商店で買い物をするときに必要なのが10元札。しかし、両替時には100元札や50元札の大きな額のお札が多くなってしまうなど、中国では細かいお金が極端に不足する場合が少なくない。買い物に訪れたついでに、両替しておくと便利だ。この機械にはニセ札を識別するための機能もあるので安心して利用できる。 空港ではタクシーなどお小遣い分の両替にとどめ、自分の宿泊するホテルで必要額を2-3日ごとに両替するのが賢明。両替時は原則としてパスポートを提示する。 中国元は6000元まで持ち出し可能だが、日本での両替はできない。出国時に元を日本円に再両替する際は、両替時に発行された外貨兌換証明書を提示しなくてはならないので、大切に保育しておくこと。 ◎時差(2002年4月) 日本との時差は1時間。日本よりも1時間、遅れている。(-1時間)国内においてはエリアによる時差やサマータイムはない。ただし、西部の新疆エリアにおいては、非公式の新疆時間(正式な時間=通称:北京時間)が存在する。 ◎ビザ(2003年9月) 中国に渡航する際には必ずビザを取得しなければならない。一般の観光の場合は「Lビザ」を取得する。これは1回の入国が可能な1次ビザと、3か月間に2回入国できる2次ビザ(いずれも滞在期間は、1回につき30日以内)の2種類がある。 ただし、2003年9月1日より、観光、商用、親族訪問又は通過の目的で中国へ入国する場合は、滞在日数が15日以内であれば、ビザなしで入国できることになりました。 ビザの申請には、残存有効期間が4か月以上あるパスポート、ビザ申請書、写真(4×3センチ)、中国での受け入れ先が発行する招聘状(インビテーション)が必要となるが、通常は旅行会社に手続きの代行を依頼するため、パスポートと写真を用意するだけでいい。 費用は旅行会社によって異なるが、一緒に航空券を購入し、10日ほどで1次ビザを取得する場合、申請料と手数料で最低6000~7000円程度。ビザを特急(2~3日)で取得する緊急申請はプラス5000円程度が相場だ。 Lビザは、現地の公安局で原則として1回に限り延長が可能。また、香港の外交部簽證弁事処では、日本に比べて手続きが簡単で、翌日にはビザが下りる。 中国への入国時には、入国カードと健康カードを提出する。いずれも、氏名、生年月日、国籍、パスポート&ビザ番号、滞在先などを記入しなければならないが、日本語(漢字)やローマ字で書いてもOK。また、滞在先が未定の人でも、北京なら「北京飯店」、上海なら「和平飯店」といった有名ホテルを記入しておけば問題ない。 ・ビザなし短期訪問について(2003年8月25日、中華人民共和国駐日本大使館HP) 1. 2003年9月1日より、普通パスポートを持つ商用、観光、親族訪問、トランジットの目的で入境する日本籍の者は、入境日から15日以内の場合ノービザ。その時、必ず外国人に開放する飛行場、港から入境し、イミグレーションで有効のパスポートを提出しなければならない。 2. 2003年9月1日より、普通パスポートを持ち、15日を越えて滞在する者、或いは留学、就業、定居、取材者、及び外交、公務パスポートの者は今まで通り、現在の法律と規定に基づいて、中国大使館総領事館でビザを申請する。 3. 日本の航空会社の乗務員は今までどおり中日間の協議に基づいて行われる。 4. 15日以内の滞在のつもりで入境した日本人がもし15日を越えるような場合は、現地の公安局の入境管理部門でビザの申請をする。停留期間を超過した者は、公安機関とイミグレーションで規定に基づく処罰が与えられることになるので注意。 ◎航空会社(2002年4月) 日本から中国に就航している航空会社は、日本航空(JL)、全日空 (NH)、日本エアシステム(JD)、中国国際航空(CA)、中国東方航空 (MU)、中国西北航空(WH)、中国西南航空(SZ)、中国南方航空(CZ)、 中国北方航空(CJ)、ユナイテッド航空(UA)、ノースウエスト航空 (NW)、パキスタン国際航空(PK)、イラン航空(IR)など。 成田、関西、名古屋、広島、福岡、長崎、沖縄(不定期)、岡山、新潟、富山、福 島、仙台、札幌のいずれかの空港と、北京、上海、ハルピン、瀋陽、大連、 青島、天津、西安、武漢、重慶、アモイ、広州、桂林、昆明の間を、直行便 と経由便が結んでいる。フライト時間(直行便)は、成田?北京約3時間 半、成田?上海3時間。 ◎電気事情(2002年4月) 50Hz、220V ◎クレジットカード(2002年4月) クレジットカードはVISA、マスター、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナースなどが高級ホテル、デパート、レストランなどで使用できる。ただし、地方によってはカードが使用できないところもあるので、現金の準備が必要となる。 中国の大都市では、ホテル、有名ショッピングセンターでクレジットカードが利用できる。 ◎チップ(2002年4月) 基本的には不要。ホテルで欧米人の宿泊客が自分たちの習慣にしたがって従業員に渡していることから、当然のように要求してくるものもいるが、高級ホテルでは、いかなる場合も受け取っては行けないと教育している所もあるくらい。無理に渡す必要はない。 ◎電話(2002年4月) 電話をかける場合、最も便利なのは宿泊先のホテル。たいていのホテルは、部屋から長距離通話、国際通話が可能。 日本に国際電話をかける場合は、外線発信番号を押した後、「00(国際電話識別番号)+81(日本の国番号)+0を除いた市外局番+番号」でOK。 国内の長距離通話は、日本の市外局番にある地方コード・局番がわからない場合、部屋に備えつけてあるコード一覧などで確認したうえでダイヤルする。コレクトコールは、ジャパンダイレクト(108-811)にかければ、日本人オペレーターが対応する。 一方、公衆電話はコイン式とカード式があるほか、カード式にもICカード式と磁気カード式の2種類があり、それぞれ電話機が異なる。外出先から長距離通話をかけるには、 1)長距離通話可のカードを使用して公衆電話を利用する 2)郵電局で申し込む 3)「長途」の看板のある有人式電話を利用する などの方法がある。 また、公衆電話で国際電話をかける場合は、外国人客が比較的多いホテルや友誼商店、高級デパートなどで国際通話が可能な電話機を捜す。 ◎郵便事情(2002年4月) 郵便局は中国語で、郵電局・郵局・郵政局という。ポストはグリーンでかなり目立つ。国土が広く、場所によって郵便事情は異なるが、北京や上海からなら航空便で1週間以内に到着する。ハガキ3.2元-、封書4.4元-。 中国から日本への郵便料金は、航空便でハガキ4.2元、封書が10グラムまで5.4元、20グラムまで6.4元。いずれも1週間-10日程度で日本へ届く。大至急という場合は「EMS(国際速達)」を利用する。北京・上海からであれば3-4日で日本へ届くうえ、書留なので安心できる。宛名も日本語で問題ない。2000年7月より料金が10%程度引き下げられ、ますます利用しやすくなった。 ◎インターネット事情(2002年4月) 中国でも、インターネット環境が急速に整備されつつあり、外国人客の多い大都市のホテルでは、通信用モジュラージャックが用意されているところもみられる。電圧は220ボルトなので、自分のPCのアダプターが対応していれば問題なく使える。 北京や上海には24時間営業のインターネットカフェも多い。しかし、ネットカフェのなかには、賭博ソフトやアダルトサイトなど法律で禁じられているサイトを提供しているところもある。そのため、中国政府はネットカフェに対して、ネット記録管理ソフトの使用や客の身分証明を義務付けている。 ◎車(2002年4月) 車は左ハンドル(右側通行)です。 ◎国際電話(2002年4月) 国番号:86 ◎祝祭日(2002年4月) 中国では、伝統にもとづく風情豊かな祝祭イベントが少なくない。日本と同じように、大都市では若者を中心として、伝統的な風習に対する関心は薄れがちではあるが、農村部や南方ではまだまだ古き良き伝統が受け継がれている。 なお、「正月」と言えば、西暦1月1日ではなく、旧暦1月1日を指すことからもわかるように、その多くは旧暦(農歴)で祝うため日程には注意したい。主な祝祭日は次のとおり。(旧)は、旧暦。 1月1日:元日。新年を祝う。国民の休日(休暇は1日)。 1月1日(旧):春節。 国民の休日(休暇は3日間)。大晦日(除夕)の晩は家族で餃子を食べ、1夜寝ずに新年を迎える(守歳)。ちなみに餃子は、中国語発音が昔の紙幣(角子)と同じで、形も昔の貨幣(元宝)と似ていることから、縁起のいい料理とされている。また、春聯(赤い紙にめでたい対句が書かれた一対の短冊)が玄関に貼り出されるほか、爆竹や打ち上げ花火といった春節ならではの風物詩も残っている。農村部では龍の舞い(龍燈舞=龍の形をした長い張り子の提灯を数人で高く持って街をねり歩く)も見られる。 1月15日(旧):元宵節。 提灯を飾り、家族団らんであん入り団子(元宵)を食べる。灯籠や吊り提灯になぞなぞを書きつけておき、それを解いた人が答えを紙に書いて貼りつけておく「灯謎」と呼ばれる遊びが行われる地方もある。 3月8日:三・八国際婦女節。女性のみ半日休み。 4月5日:清明節。 墓参りをして先祖の供養をする。江南地域では、清明団子(ハハコグサで作る)を食べる風習が残っている。 5月1日:五・一国際労働節。メーデー。国民の休日。 気候がよい時期に当たるため、都市近郊は小旅行の人々で賑わう。2001年の休日は、規定通りの3日間(5月1、2、3日)以外に、4月28日(土)・29日(日)の休みを5月4日(金)・7日(月)と入れ替えて、5月1~7日まで7日間の大型連休となる。4月28日(土)・29日(日)は出勤日。 5月4日:五・四中国青年節。中学生以上は半日休み。 5月5日(旧):端午節。 古代の愛国詩人・屈原をしのぶ日と言われる。農村部では、五色の糸で作ったおもちゃを子供の体につけて厄除けをする俗習が残っているが、都市部ではチマキを食べるぐらい。 6月1日:児童節。いわゆる子供の日。小学生は休み。 7月1日:中国共産党創立記念日。 1997年からは香港祖国回帰記念日が加わった。党関係者を中心に記念行事を行う。 7月7日(旧):乞功節。七夕祭り。 8月1日:八・一中国人民解放軍記念日。 建軍節とも。1927年の南昌蜂起を記念し、人民解放軍・軍事機関関係者のみ半日休み。 8月15日(旧):中秋節。 月見を楽しみ、一家団らんで食事をする。親しい人との間で月餅を贈り合ったりもする。 9月9日(旧):重陽節。 菊の花を観賞し、菊花酒などを飲む。高いところへ登ると厄除けになることから、登山の風習もある。小学校などではこの日に遠足へ行く。 10月1日:国慶節。 国をあげて、1949年10月1日の中華人民共和国成立を祝う。国民の休日。5周年ごとに大規模なパレードなどが行われる(次回は建国55周年に当たる2004年)。 2001年の休日は、規定通りの3日間(10月1・2・3日)以外に、9月29日(土)・30日(日)の休みを10月4日(木)・5日(金)と入れ替えて、10月1~7日まで7日間の大型連休となる。9月29日(土)・30日(日)は出勤日。 ◎姓名(2005年11月) 日本と同じく、姓の後に名が来ます。女性は結婚しても姓を変えません。 ◎教育(2005年11月) 日本と同じく、6・3・3制です。 ◎中国の人の給料について(2002年7月29日) 人材派遣会社「テンプスタッフ上海」に問い合わせた情報です。客観的な給料に関する統計データはないようです。基本的には、企業側と採用予定者が協議の上で決定するようです。下記に、参考的な給与の例をまとめます。(上海、北京での参考データ) ・日本語が話せる人(1ヶ月あたり) 女性 20~25才:2,500~3,500人民元くらい 25~35才::5,000人民元くらい 20~30才(大卒):3,000~5,000人民元 男性 20~30才(大卒):3,000~6,000人民元 30~35才(大卒):6,000~8,000人民元 35才以上は、不明(双方協議して決定するそうです。) ◎中国の人の給料について(2006年5月) 宜興市で働く中国人に聞いた情報です。(1ヶ月あたり) ・無錫で日本語が話せる人を雇った場合:4,000~5,000人民元 ・宜興市の会社の給料 社長:5,000人民元くらい 部長:2,000人民元くらい |
| ◎略史 中国、アジア大陸の東部に出現した歴代王朝の通称。きわめて古い時代に黄河中流域に定住した漢民族の開いた国で、古来、漢民族は周辺の外民族を蛮夷と称し、自らは世界の中心にあることを誇りにしてこれを自称。以来、この地に建国した王朝はほとんどこの名称を用いたが、領土の発展によってその範囲は時代とともに拡大。 殷・周・秦・漢時代には、ほぼ華北に限定されていたが、三国・晋・南北朝時代には江南、唐代には広東、宋代に福建・江西、明代に雲貴・広西の各地にまで広がり、清代にはさらに満州・蒙古などの一部に及んだ。さらに第一次・第二次世界大戦を経て、一九四九年、中華人民共和国の成立以来、その領土はすべて中国と規定されている。 1911年 辛亥革命によって清朝滅亡。中華民国誕生。(中国史上初の共和国) 1912年 中華民国成立。 1921年 中国共産党創立。 1949年10月1日 中華人民共和国誕生。国家主席、毛沢東。 国務院総理(内閣総理大臣)および、外交部長(外務大臣)、周恩来。 1950年~1952年 土地改革。地主の土地が没収されて農民に分配された。 チベットを中国の領土と主張し、中国解放軍がチベットに侵入、制圧。(1950年) (当時のチベットは神政国家。ダライ・ラマを頂点とし、一握りの僧侶、貴族が農民を使役していた。) 1953年 第一次五ヶ年計画(重工業優先) 1956年 第二次五ヶ年計画 1959年 ラマ教僧侶を中心とした反乱が発生。 ダライ・ラマ14世がインドに亡命。インドと国境紛争が発生。 1962年 インドと武力衝突。 1966年~1969年 文化大革命。劉少奇、鄧小平が失脚。劉少奇は幽閉中に死亡。 1976年 毛沢東、周恩来が死去。 1977年 鄧小平が共産党副主席になる。文化大革命の終結宣言。 1978年 日中平和友好条約 1979年 米中国交正常化 1980年 鄧小平のグループの趙紫陽が国務院総理になる。 中ソ友好同盟相互援助条約、失効。 1981年 鄧小平のグループの胡耀邦が党主席になる。 鄧小平は党中央軍事委員会として軍を掌握し、実権を握る。 歴史決議によって文化大革命が誤りであったことを確認。 1982年 党主席を廃止。胡耀邦が党総書記になる。 1988年 趙紫陽が党総書記になる。 1989年 趙紫陽が党総書記を解任される。 |
| 便利なサイト 人民日報 中国経済 上海日本総領事館 中国情報局 中国情報 |